Contentsお役立ち情報・製品動画
お役立ち 2025.10.31
看護小規模多機能居宅介護(看多機)とは?特徴3つや起きやすい課題と解決策

「看多機って何のための施設?」
「小多機との違いがわからない」
このように感じる方も多いでしょう。
看護小規模多機能型居宅介護(看多機)は、医療ケアが必要な方でも在宅で暮らし続けられるよう支援する、柔軟性の高いサービスとして注目されています。※小多機について説明は後述いたします。
しかし、その柔軟さゆえに、現場では職員の負担の増大や情報共有の難しさといった課題も生じやすい環境です。
この記事では、看多機の基本的な仕組みと特徴、現場で起こりやすい課題とその解決策を解説します。
最後までお読みいただくと、看多機の全体像や、ICTの活用といった具体策を知ることができ、より働きやすい環境づくりのヒントが得られます。ぜひ参考にしてください。
▼目次
- 1.看多機は通い・訪問・泊まり・訪問看護で在宅生活を支えるサービス
- 看多機の利用条件
- 看多機の人員基準
- 看多機と小多機の違い
- 2.看多機の特徴3つ
- 1.通い・訪問介護・泊まり・訪問看護を一体的に提供できる
- 2.サービス間をスムーズに移行できる
- 3.医療ケアにも対応しやすい体制がある
- 3.看多機で生じやすい課題・デメリット
- 看護師・介護職の業務負担の増大
- 配置基準の複雑さと人材確保の困難
- 医療・介護の役割分担が不明瞭になりがち
- 外部サービスの利用制限
- 情報共有の難しさと伝達ミスのリスク
- 4.看多機で起こりやすい課題を解決する方法
- 柔軟なシフト設計
- サービス運用の見直し
- 記録業務や連絡手段のICT化
- 夜間対応の効率化
- 多職種間での情報連携とチームケアの強化
- 5.看多機で働くスタッフの「しんどい」を減らすにはICT・DX導入が有効
1.看多機は通い・訪問・泊まり・訪問看護で在宅生活を支えるサービス
「看護小規模多機能型居宅介護」、通称「看多機(かんたき)」は、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるための介護保険サービスです。
通い・訪問介護・泊まり・訪問看護という4つの機能を1つの事業所で提供することで、医療と介護の両面からご利用者を支援します。
ただし、看多機を利用できる方には条件があります。
人員基準とともに、看多機の基本をチェックしましょう。
看多機の利用条件
看多機を利用するには、要介護1〜5の認定が必要です。
原則として、1つの看多機事業所に最大29名までのご利用者が登録でき、1日に通える人数や泊まれる人数にも上限が定められています。
訪問看護が含まれるため、医療ニーズが高いご利用者にも対応できる一方で、ほかの居宅サービスとの併用が制限される点も特徴です。
看多機の人員基準
看多機では、以下のような人員配置が義務付けられています。
| 職種 | 配置基準 |
|---|---|
| 代表者 | 1名 |
| 管理者 | 常勤専従1名 |
| 看護職員(事業所全体) | 常勤換算法で2.5名以上(保健師、看護師、准看護師のいずれかで最低1名は常勤) |
| 介護職員 | <日中> ・通いサービス:ご利用者3名に対し1名以上(常勤換算) ・訪問サービス:2人以上(常勤換算) <夜間・深夜> ・泊まり、訪問サービス:2名以上(うち1名は宿直勤務可) |
| 計画作成担当者(ケアマネジャー) | 1名以上 |
看多機では、通いと訪問看護のそれぞれに1名以上の看護職員(看護師・保健師・准看護師)を配置します。
ただし、通いと訪問看護に別々の看護職員を置く必要はなく、同じ職員が兼務することも可能です。
1人の看護師が午前は通い、午後は訪問を担当するといった形でも、人員基準を満たしたことになります。
看多機と小多機の違い
看多機は「看護小規模多機能型居宅介護」、小多機は「小規模多機能型居宅介護」を指し、両者の違いは「訪問看護」の有無です。
小多機では通い・訪問介護・泊まりの3つのサービスを提供しますが、訪問看護は含まれません。
一方、看多機では訪問看護が含まれ、看護師による医療ケアが提供できるため、痰の吸引や胃ろう管理、褥瘡ケア、看取りなど、医療依存度が高いご利用者にも対応できます。
また、小多機に比べて人員体制や制度運用が複雑なことから、医療職と介護職の連携がより重視される傾向があります。
▼参考:看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)|厚生労働省
▼参考:看多機のご紹介|日本看護協会
▼参考:看多機の運営に関するQ&A集|日本看護協会
2.看多機の特徴3つ
看多機には、ほかの介護サービスにはない独自の特徴があります。
代表的な3つの特徴を解説します。
1.通い・訪問介護・泊まり・訪問看護を一体的に提供できる
1つの事業所で、通い・訪問介護・泊まり・訪問看護の4つのサービスを柔軟に組み合わせて提供できる点が、看多機ならではの特徴です。
たとえば、普段は週3回の通いサービスを利用している方が、体調を崩したときだけ訪問看護や泊まりサービスに切り替える、といった使い方が可能です。
この柔軟性は、ご利用者の状態変化に素早く対応できるだけでなく、ご家族の介護負担の軽減にもつながります。
2.サービス間をスムーズに移行できる
同じ事業所内のスタッフがかかわるため、サービス間の移行がスムーズです。
通っていたご利用者が体調を崩した際に、そのまま泊まりに切り替えたり、訪問看護に移行したりといったケアの連続性が担保されます。
環境が変わらず、顔なじみのスタッフが対応することで、ご利用者の安心感や、ご家族の負担軽減にもつながります。
また、サービス提供者側も、日頃からご利用者の生活状況や好みを把握しているため、状態変化に気づきやすく、きめ細かに対応できるのがメリットです。
3.医療ケアにも対応しやすい体制がある
看多機では看護師の配置が義務付けられており、以下のような処置が必要な医療依存度の高いご利用者にも対応可能です。
● 痰の吸引
● 褥瘡(床ずれ)の処置
● インスリン注射
● 胃ろうや経鼻栄養の管理
● 看取りケア
「病院を退院したけれど、医療的なケアが必要で自宅だけでは不安」という方にとって、看多機は在宅生活を継続するための重要な選択肢となっています。
3.看多機で生じやすい課題・デメリット
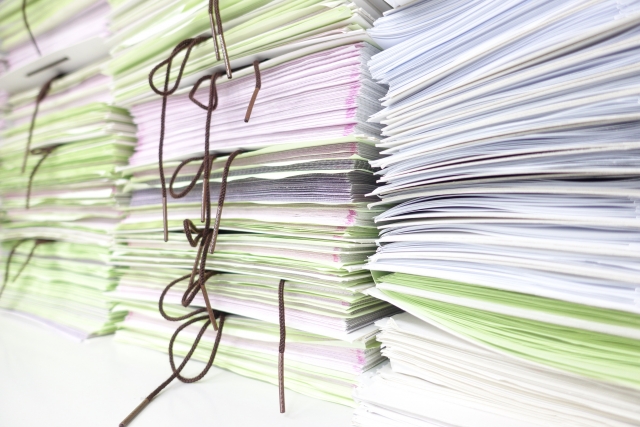
柔軟性と専門性を兼ね備えた看多機ですが、いくつかの課題やデメリットも存在します。
詳しく見ていきましょう。
看護師・介護職の業務負担の増大
看多機の魅力はサービスの柔軟性ですが、それは同時に職員が多様な業務に対応する負担にもつながります。
「訪問介護」「通い」「泊まり」「訪問看護」を切り替えながら対応するため、スタッフの心理的・身体的負担は大きくなりがちです。
とくに少人数体制の事業所では、一人のスタッフが複数の役割を担うこともあり、疲弊しやすい環境といえます。
また、夜間対応や緊急時の呼出など、不規則な勤務が発生しやすい点も、職員の負担を大きくする要因です。
配置基準の複雑さと人材確保の困難
看護師・介護職それぞれに配置基準があるうえに、看護師の確保ができなければ訪問看護を提供できないため、採用難・人材定着の課題も深刻です。
日本看護協会の「看護小規模多機能型居宅介護の普及等に関する調査研究事業」によると、看多機の開設や運営で感じる困難のうち、介護職員の確保が78.8%ともっとも多く、看護職員の確保が72.4%と続く結果となりました。
人材不足により、本来提供できるはずの医療ケアが十分におこなえない、新規ご利用者の受け入れを制限せざるを得ないといった事態も起こり得ます。
▼参考:看護小規模多機能型居宅介護の普及等に関する調査研究事業|日本看護協会
医療・介護の役割分担が不明瞭になりがち
看多機では、看護師と介護スタッフの業務の境界があいまいになりやすいことが課題のひとつです。
褥瘡(床ずれ)処置の場面を例にあげると、処置自体は看護師がおこないますが、その後の体位変換や清拭などは介護職が対応すべきか、看護師が一貫して対応するべきか判断に迷うケースがあります。
こうしたあいまいさから、業務分担の不公平感や対応ミス、責任の押し付け合いに発展する恐れがあります。
外部サービスの利用制限
看多機を利用している間は、原則としてほかの事業所の訪問介護や短期入所などのサービスが制限されます。
ご利用者によっては「これまで使っていたサービスが使えなくなり困る」と戸惑うケースもあり、デメリットと捉える方も少なくありません。
そのため、看多機に登録する前に、十分な説明と同意が必要です。
ただし訪問看護の場合は、看多機の事業所が医療保険による訪問看護の指定を受けていない、ご利用者が自宅にいるなどの場合は、併用できるケースもあります。
▼参考:看多機の運営に関するQ&A集|日本看護協会
情報共有の難しさと伝達ミスのリスク
看多機は1つの事業所内で複数のサービスを提供するため、情報共有しやすいと思われがちです。
しかし、実際の現場では、通い・訪問介護・泊まり・訪問看護にそれぞれ異なるスタッフが対応し、多職種での情報連携が不可欠な構造となっています。
申し送りが紙や口頭に頼っている場合、リアルタイムでの情報共有が難しく、伝達漏れや認識のズレが発生するリスクもゼロではありません。
ご利用者の状態変化や対応履歴が十分に共有されていないと、ケアの質の低下や事故の要因にもつながります。
看多機の訪問看護については、下記の記事で詳しく解説しています。
是非ご覧ください。
▼看多機の訪問看護とは?看護師の役割5つとICT活用のメリット
4.看多機で起こりやすい課題を解決する方法
課題も多い看多機ですが、工夫と仕組みづくりによって現場の負担を減らし、サービスの質を高められます。
具体的な解決策を解説します。
柔軟なシフト設計
訪問・泊まり・通いが同時並行で発生するため、役割と時間帯を細かくわけたシフトが重要です。
たとえば、午前中は通いサービスに専念するスタッフ、午後は訪問に回るスタッフ、夜間は泊まり対応に入るスタッフというように、業務を明確にわけることで、一人あたりの負担を軽減できます。
無理のない勤務体制が組めれば、職員の定着率向上にもつながるでしょう。
サービス運用の見直し
通い・訪問・泊まりのバランスを見直し、偏りすぎないサービス提供を心がけることが重要です。
とくに「泊まり」が増えすぎると、夜間の限られたスタッフで多くのご利用者を見守る必要が生じ、一人ひとりへのケアが手薄になる恐れがあります。
緊急対応や夜間の介護負担も増すため、職員の疲労もたまりやすくなるでしょう。
看多機は「自宅で暮らし続ける」ための支援が本来の目的です。
「ご利用者の在宅生活を支える」という制度の趣旨から外れないよう、適切なサービスバランスを保ち、スタッフの負担軽減とご利用者の在宅生活支援を実現することが大切です。
記録業務や連絡手段のICT化
記録や情報共有の非効率さは、適切なICTツールの導入で改善できます。
日本看護協会「看護小規模多機能型居宅介護の普及等に関する調査研究事業」によると、多くの看多機で電子カルテが導入されているものの、看多機に特化したシステムがなく、既存システムを組み合わせて使用しています。
その結果、記録とレセプトが連動せず二重入力が必要になったり、一部は紙カルテと併用していたりと、かえって業務が煩雑になるケースも少なくありません。
一方、カルテ共有システムを導入している事業所では、主治医やケアマネジャーとタイムリーに情報交換でき、連携の質が向上しています。
事業所に合ったICTツールの導入が、記録業務の負担軽減と連携強化の両立につながるでしょう。
▼参考:看護小規模多機能型居宅介護の普及等に関する調査研究事業|日本看護協会
電子カルテと連携できるシステムに関しては、下記の記事で解説しています。
▼電子カルテと連携できるシステムと標準化の背景|メリット・課題を解説
夜間対応の効率化
夜勤体制では人員が限られるため、見守りセンサーやナースコールの連携によって、スタッフの負担を減らせます。
たとえば、ベッドからの離床を感知するセンサーや、転倒リスクの高いご利用者の動きを検知するシステムを導入することで、巡回の頻度を減らしながらも安全を確保できます。
また、緊急対応を事前に予測し、対策を講じる仕組みも有効です。
夜間の急変時対応マニュアルの整備や、医療機関との連携体制の確認など、しっかり準備しましょう。
多職種間での情報連携とチームケアの強化
看護師・介護スタッフ・ケアマネジャー・訪問医など、多職種が密に連携する体制を整えることで、サービスの質向上と業務効率化が可能です。
具体的には、ケアコムが提供する総合医療介護連携システム「CoEsse」のようなICTツールの活用によって、現場でのリアルタイムな共有がスムーズになり、ご利用者の状態変化に素早く対応できます。
多職種が同じ情報を見ながらケアにあたることで、役割分担の明確化と連携強化が実現できるでしょう。
5.看多機で働くスタッフの「しんどい」を減らすにはICT・DX導入が有効

看多機は、ご利用者にとって柔軟で安心感のあるサービスです。医療ケアが必要な方も住み慣れた地域で暮らし続けられる、貴重な選択肢といえます。
しかし、その運営には職員の負担増大や人材確保の難しさ、情報共有の複雑さなど、いくつかのハードルがあります。
現場の「しんどさ」を放置せず、ICTやDXの力を活用して課題に向き合うことで、持続可能で高品質なサービス提供が実現できるでしょう。
ケアコムでは、ナースコールシステムや情報連携ツールなど、看多機運営に役立つ多彩なソリューションを提供しています。
また、看多機運営にとって大切な医療・介護の地域連携について、下記の無料資料にまとめています。
\ぜひダウンロードしてみてください/


