Contentsお役立ち情報・製品動画
お役立ち 2025.10.09
【診療報酬改定】2026年度はいつ?5つの改定ポイントを予想
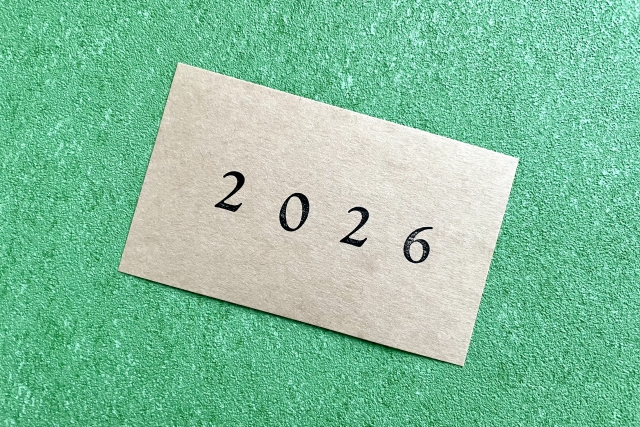
診療報酬改定は、病院やクリニックの経営にかかわる制度です。
そのため「2026年度の改定はいつから始まるのか」「どんな点が変わるのか」と気になって検索した方も多いのではないでしょうか。
この記事では、2026年度診療報酬改定の施行時期やスケジュール、注目される5つの改定ポイントを整理しました。
早めに方向性を押さえておけば、直前で慌てることなく準備が進められます。
▼目次
- 1.2026年度診療報酬改定の施行時期
- 2.2026年度診療報酬改定のスケジュールと必要性
- 中医協での審議スケジュールと厚生労働省の役割
- 診療報酬の基本の仕組みと改定の背景
- 3.2026年度診療報酬改定のポイント5つと予想される影響
- 1.医療機関の経営基盤の強化
- 2.人員配置より「成果」を重視
- 3.医療DXの推進
- 4.在宅医療推進のための仕組みの強化
- 5.医師の働き方改革への対応
- 4.2026年度診療報酬改定から見える「医療DX」の重要性
- 5.2026年度診療報酬改定に向けて今から準備できること
- 院内共有・体制構築・医療DX導入検討
- 情報収集とスケジュール管理
- 6.2026年度診療報酬改定への備えを今から始めましょう
1.2026年度診療報酬改定の施行時期
2.2026年度診療報酬改定のスケジュールと必要性
2026年度の診療報酬改定に向けて、すでに中央社会保険医療協議会(中医協)を中心に議論が進んでいます。
施行までの押さえておきたい流れを確認しておきましょう。
中医協での審議スケジュールと厚生労働省の役割
2026年度の診療報酬改定までの流れは、以下のとおりです。
| 項目 | 時期 | 内容 |
|---|---|---|
| 議論開始 | 2025年4月~ | 中医協を中心に大まかな改定方針の話し合いを開始 |
| 細かいルールの検討 | 2025年10月~12月 | 医療の「点数」をどう変えるか、各部門で具体的な内容を決定 |
| 改定率の決定 | 2025年12月 | 医療機関の収入に直結する「どれくらい増やすか、減らすか」という数字(改定率)が決定 |
| 答申・告示 | 2026年1月~3月 | 中医協から厚生労働大臣に確認、その後告示 |
| 施行時期 | 2026年6月以降(予想) | 医療機関での実際の改定内容が施行 |
▼参考:令和8年度診療報酬改定に向けた主な検討スケジュール(案)|厚生労働省
こうしたスケジュールで審議を進め、最終的には厚生労働省がとりまとめて厚生労働大臣の告示によって正式に決定します。
つまり、中医協が「審議の場」、厚生労働省が「決定と実行の責任主体」という役割を担っています。
診療報酬の基本の仕組みと改定の背景
診療報酬とは、病院やクリニックが提供する医療サービスの「値段」を国が定めたものです。診察、検査、手術、薬などにそれぞれ点数が割り振られ、これにもとづいて請求がおこなわれます。
改定するおもな理由は、以下のとおりです。
● 物価や人件費の変動:物価上昇や医療職の賃上げに対応するため
● 医療技術の進歩:新しい医療技術や治療法を評価するため
● 社会の変化:高齢化の進展や人口減少などの社会ニーズに合わせるため
近年はとくに「人件費の高騰」と「働き方改革」の課題が大きくなっています。
そのため2026年度の診療報酬改定も、単なる点数調整ではなく、現場が無理なく医療を続けられる仕組みづくりが求められています。
3.2026年度診療報酬改定のポイント5つと予想される影響
2026年度の診療報酬改定は、物価や人件費の高騰、高齢化、そして医師の働き方改革といった課題に対応する内容になると見込まれています。
経営や業務体制にかかわる5つのポイントを解説します。
1.医療機関の経営基盤の強化
エネルギー費や物価、人件費の上昇で、多くの病院・診療所の経営が圧迫されています。
そのため医療界からは、診察料や入院料など基本的な報酬の引き上げを求める声が強まっています。
改定が実現すれば、病院や診療所の収入が増え、物価や人件費の上昇分をカバーできます。結果として、経営の安定や医療サービスの継続につながるでしょう。
ただし、財源には限りがあるため、大幅な引き上げは簡単ではない点に注意が必要です。
2.人員配置より「成果」を重視
これまでは「どのくらい多くの職員を配置しているか(人員配置)」で評価される仕組みが中心でした。
しかし2026年度の診療報酬改定に向けて、日本病院団体協議会が「患者さんにどのような成果があったかを重視すべき」という要望書を提出していることから、評価基準が結果重視に変わる可能性があります。
少子高齢化で人材確保が難しいなか、今後は「人数より成果」で評価する流れが強まると見込まれます。
3.医療DXの推進
電子カルテの標準化やオンライン診療、処方せんデータの共有など、医療のDX(デジタル化)は避けられない課題です。
厚生労働省も「地域の医療提供体制の維持・確保する観点から、医療DXの推進が欠かせない」としていることからも、何かしらの改定がおこなわれると推測できます。
医療DXにおいては、初期費用やランニングコストが高くなりがちな点が課題です。
補助金だけではまかないきれないため、診療報酬でどのように後押しするかが注目されます。
電子カルテと連携できるシステムなどについては、下記の記事で紹介しています。
是非ご覧ください。
▼関連記事:電子カルテと連携できるシステムと標準化の背景|メリット・課題を解説
4.在宅医療推進のための仕組みの強化
2026年度の診療報酬改定では、訪問診療や訪問看護の評価が手厚くなると予想されます。
厚生労働省の「患者調査」をもとにした見解によると、85歳以上の在宅医療の需要は2020年から2040年にかけて62%増える見通しです。
こうした需要の増加を背景に、住み慣れた地域で医療を受けられる仕組みが一層強化されると考えられます。
5.医師の働き方改革への対応
2026年度の改定では、医師の負担軽減とチーム医療の推進がテーマのひとつになると考えられます。
背景には、2024年から医師の時間外労働に上限が設けられたことがあります。
これに対応するため、医師の業務を他職種に任せる「タスクシフト/タスクシェア」がさらに広がる見込みです。
なかでも、日本病院団体協議会の要望書で示された「医師事務作業補助者」へのタスクシフトは、業務負担の軽減に効果があると評価されています。
宿日直の規制緩和やICU要件の見直しも議論される可能性があり、働き方改革を支える仕組みが整備されていくと考えられます。
4.2026年度診療報酬改定から見える「医療DX」の重要性

2026年度診療報酬改定では、限られた人員で医療の質を守るために医療DXの推進が不可欠と考えられます。
電子カルテや処方せんデータの共有、オンライン診療などを活用すれば、業務を効率化しながら患者満足度も高められます。
人材不足や働き方改革に直面する現場にとって、DXは無理なく医療の質を保ち続けられるポイントとなるでしょう。
ただし導入や維持には大きなコストがかかり、補助金だけでは十分とはいえません。
そこで注目されるのが、現場負担を減らしつつ運用まで支援できる仕組みやサービスです。
ケアコムはナースコールや情報連携を中心に、医療安全と効率化を両立させる製品を展開しています。
改定に振り回されないためにも、現場の状況に合ったDXを早めに検討しておくことが安心につながります。
▼ケアコムの医療施設用製品・システムをみる
5.2026年度診療報酬改定に向けて今から準備できること
診療報酬改定に備えてスケジュールを把握しつつ、院内での情報共有や体制づくりを早めに進めることが大切です。
ここでは、今から始められる準備のポイントを紹介します。
院内共有・体制構築・医療DX導入検討
診療報酬改定への対応は、一部のスタッフだけでなく、現場全体での意識共有が欠かせません。
説明会や勉強会を開き、方向性や起こりうる影響を全員ですり合わせましょう。
とくに医療DXは制度対応にとどまらず、業務効率化や患者満足度の向上にもつながります。
2026年度改定前の今こそ、導入を検討し始めるよいタイミングです。
▼関連記事:医療DXとは?4つの取り組み事例と医療DXが進まない理由を解説
情報収集とスケジュール管理
2026年度の診療報酬改定の内容は、中医協や厚労省の審議を通じて段階的に明らかになります。
夏から秋にかけての分科会、年末の改定率決定、年明けの短冊公表など、重要なタイミングを逃さないようにしましょう。
定期的に最新情報を共有できる仕組みを整えておけば、直前に慌てることなく対応できます。
計画的に準備することが、改定をチャンスに変える第一歩です。
6.2026年度診療報酬改定への備えを今から始めましょう

2026年度の診療報酬改定は、医療機関にとっての節目です。
施行時期やスケジュール、注目すべき5つのポイントを理解しておけば、直前で対応に追われることもありません。
人材不足や働き方改革など厳しい環境のなかでも、医療DXを取り入れ、院内で協力しながら体制を整えることが重要です。今から少しずつ備えを進め、2026年度の改定を安心して迎えましょう。
ケアコムでは、医療DXをテーマにした資料を無料公開しています。
\改定準備の参考資料として、ぜひご活用ください/



