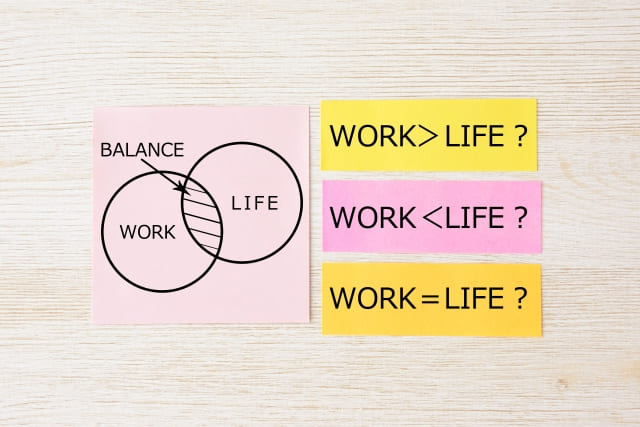Contentsお役立ち情報・製品動画
お役立ち 2025.02.07
看護師の離職率は11.8%!高いといわれる理由と高い病院の特徴を徹底解説

「看護師の離職率ってどのくらい?」
「離職率が高い病院って特徴があるの?」
このように疑問を抱く看護師の方もいらっしゃるのではないでしょうか?
2022年度の看護師の離職率は11.8%で、全産業と比べて低い傾向です。それでも「離職率が高い」といわれるのは、看護師の働き方や職場環境の課題があるためといえるでしょう。
この記事では、看護師の離職率が高いとされる理由や高い病院の特徴、離職率を下げる対策まで解説します。
看護師を職場に定着させたいと考える方は、ぜひ参考にしてください。
▼目次
1.看護師の離職率は11.8%【2024年発表】
看護師の離職率は、2022年度で11.8%です。同年の全産業の離職率が15.0%であるため、看護師の離職率は平均以下といえます。
| 調査年 | 看護師全体 | 新卒 | 既卒 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 11.8% | 10.2% | 16.6% |
| 2021 | 11.6% | 10.3% | 16.8% |
| 2020 | 10.6% | 8.2% | 14.9% |
▼参考:公益社団法人日本看護協会「「2023年 病院看護実態調査」 結果」
看護師の離職率は、新人・既卒に関係なく新型コロナウイルス感染症が流行した2021年から上昇しており、多くの病院が退職者が増えた影響を示しています。
2.看護師の離職率が高いといわれる理由
● 過酷な労働環境
● 給与や待遇の問題
● 身体的・精神的負担の大きさ
看護師の特殊な労働形態や仕事内容に見合った給与ではないという認識が、離職率が高いと思われる理由といえます。
過酷な労働環境
看護師の労働環境は、次のような理由からほかの職種と比較してもとくに厳しいといえます。
● 長時間労働の日常化
● 休暇取得の難しさ
たとえば、2交代制の夜勤では勤務前・勤務後それぞれ30分の残業をしている看護師の割合がもっとも多いことがわかっています。勤務時間が12時間を超えることもあり、身体的・精神的な負担が蓄積しやすい環境といえるでしょう。
また、人員不足が原因で希望するタイミングで休暇を取得できない看護師も存在します。リフレッシュする機会を得られないと、ワークライフバランスが保てずに離職を考える一因となり得ます。こうした過酷な環境が、看護師の離職をうながす要因のひとつです。
給与や待遇の問題
看護師は高度な専門知識や技術、責任感が求められる職種でありながら、報酬が見合っていないと感じることが少なくありません。
とくに都市部で働く看護師は、高い生活コストに対して十分な収入が得られず、不満を抱えるケースがあります。昇給制度やインセンティブがあいまいで、職場での自分の将来像が見えにくいこともモチベーションの低下を招きやすいです。
こうした状況では働き続ける意欲を保つことが難しく、結果として離職率の上昇につながります。
身体的・精神的負担の大きさ
看護師の業務には、身体的・精神的負担が大きい側面があり、離職の一因となっています。
| 看護師の負担 | 具体例 |
|---|---|
| 身体的負担 | ● 複数回の夜勤 ● 日常的な残業 ● 長時間の立ち仕事 ● 患者さんの移動・体位変換の介助 |
| 精神的負担 | ● 命をあずかる責任感 ● 突発的な緊急事態への対応 ● 患者さんや家族からのクレーム対応 |
とくに精神的負担は大きく、看護管理者が考える新人看護師のおもな退職理由のうち「精神的な健康上の理由」が49.4%ともっとも多いです。
からだにも心にも負担が積み重なると心身のバランスが崩れ、最終的に離職を選択する看護師が増えることにつながります。
3.看護師の離職率が高い病院の特徴|看護師がやめる3つの原因

看護師が「やめたい」と思う病院には、以下の特徴があります。
● 人員不足
● 教育・研修制度の不備
● コミュニケーション不足
離職率の高い病院の特徴がわかると、病院での対策方法が明らかになります。
ひとつずつ見ていきましょう。
人員不足
人員不足が続く病院では、1人の看護師が担当する患者数が多くなり、負担は増える一方です。本来のケアに集中する時間が減り、雑務や急な対応に追われる状況が日常化します。
また、業務量の多さから十分な休憩時間が確保できず心身の疲労が蓄積し、仕事への意欲を失う看護師もいます。こうした過酷な環境が続けば、最終的に離職を選ぶ看護師が増えるのは避けられないでしょう。
教育・研修制度の不備
教育や研修制度が整備されていない病院では、適応に苦しむ看護師が少なからずいます。
とくに現場でのサポートが不十分であると、スキル不足への不安や孤立感が深刻化し、早期離職につながるケースが見られます。
日本看護協会の調査でも、新人看護師の離職理由の上位に「看護職員としての適性への不安」や「看護実践能力への不安」があがりました。既卒看護師にとっても、キャリアアップや質の向上のための研修制度が整備されていない病院は魅力が薄れ、転職を考える要因となるでしょう。
▼参考:公益社団法人日本看護協会「『2023年 病院看護実態調査』 結果」
コミュニケーション不足
職場内の人間関係が希薄で業務連携やサポートが十分でない環境では、看護師のストレスが蓄積し退職者が増える原因となります。
実際、新人看護師の退職理由のうち「上司や同僚との人間関係」が27.6%を占めました。
こうした状況に対応するため、定期的なミーティングや相談窓口の設置など、組織内のコミュニケーションを強化する取り組みが必要です。
4.看護師の離職率を下げるために病院ができること
● 職場環境の整備
● メンタルヘルスの強化
● 教育・キャリア支援の充実
課題に合わせた対策をとることで、看護師が誇りと喜びをもって働ける職場環境を実現できるでしょう。
職場環境の整備
看護師が安心して長く働くには、職場環境の整備が欠かせません。
具体的な方法は以下のとおりです。
| 対策 | 具体例 |
|---|---|
| 業務効率化の向上 | ● 電子カルテやICTの導入 ● タスクシフト/シェアの推進 |
| 休暇の取得促進 | ● 勤務中の適切な休憩の促し ● 有給休暇を取りやすい制度の整備 |
| 福利厚生施設の充実 | ● 勤務中の適切な休憩の促し ● 休憩室、仮眠室などの整備 |
| シフトの見直しによる労働時間の短縮 | ● 長時間労働の改善 ● さまざまな勤務形態の導入 |
こうした職場環境の改善によって看護師が負担の軽減を実感でき、働き続けやすい環境を作れるでしょう。
メンタルヘルスの強化
看護師は精神的負担も大きいため、メンタルヘルスを支える環境の整備が離職の防止につながります。
具体例として以下があげられます。
● 定期的なストレスチェック
● メンタルヘルスに関する研修
● 病院内に専任のカウンセラーや相談窓口を設置
新人看護師の離職理由でメンタル不調が上位であったことからも、看護師のメンタルヘルス対策は離職率の低下に重要な役割を果たすといえるでしょう。
教育・キャリア支援の充実
看護師が成長を実感でき、明確なキャリアビジョンを描ける環境の提供も、離職率を下げる方法のひとつです。
たとえば、キャリア支援のためのラダー制度を活用した事例では、離職率が低下する結果が得られました。
病院が教育やキャリア支援に力を入れることで、看護師が将来に希望を持って働き続けられ、職場への定着につながるでしょう。
5.看護師の離職率を低下させた成功例

看護師のタスクシフトをおこない、院内制度を利用しやすい環境を整えたことで離職率が低下した事例を紹介します。
| 取り組んだ内容 |
|---|
| ● さまざまな勤務体系の整備とそれに合わせた看護提供方式(PNS:パートナーシップ・ナーシング・システム※)の採用 ● 産休、育休中職員のスムーズな復職支援(e-learningの活用、託児所を併設した勉強会など) ● 医療クラークによる入院患者情報の事前入力(タスクシフト) |
| 得られた結果 |
| ● 離職率の低下:平成28年度11%→平成29年度7.6% ● e-learningの高い利用率:現職員80%以上、産休・育休中スタッフの利用率20~30% ● 「業務負担の軽減を実感した」と答えた看護師の増加 |
※PNSは国立大学法人福井大学の登録商標です。
▼参考:いきいき働く医療機関サポートWeb(いきサポ)「タスクシフトの推進と各種制度を利用しやすい環境作りに関する取組」
看護師の離職を防ぐには、事例のように病院の課題に合わせた対策をいくつか同時におこなうことも効果的といえるでしょう。