Contentsお役立ち情報・製品動画
お役立ち 2023.06.18
離床センサーのデメリットと補う対策とは?メリットや導入時の注意点も解説

ベッドや床に敷いて活用する離床センサーは、患者さん・ご利用者の転倒・転落や徘徊行動を防ぐことできます。しかし、離床センサーを活用するなかで「誤報が多く職員の負担が増加している」「センサーを避けられてしまう」などの課題が生じていませんか。
本記事では看護・介護職員に向けて、離床センサーのメリット・デメリット、導入時の注意点やポイントを解説します。デメリットを補う対策や種類別の離床センサーのメリット・デメリットも解説していますので、ぜひ参考にしてください。
▼目次
1.離床センサーのデメリット
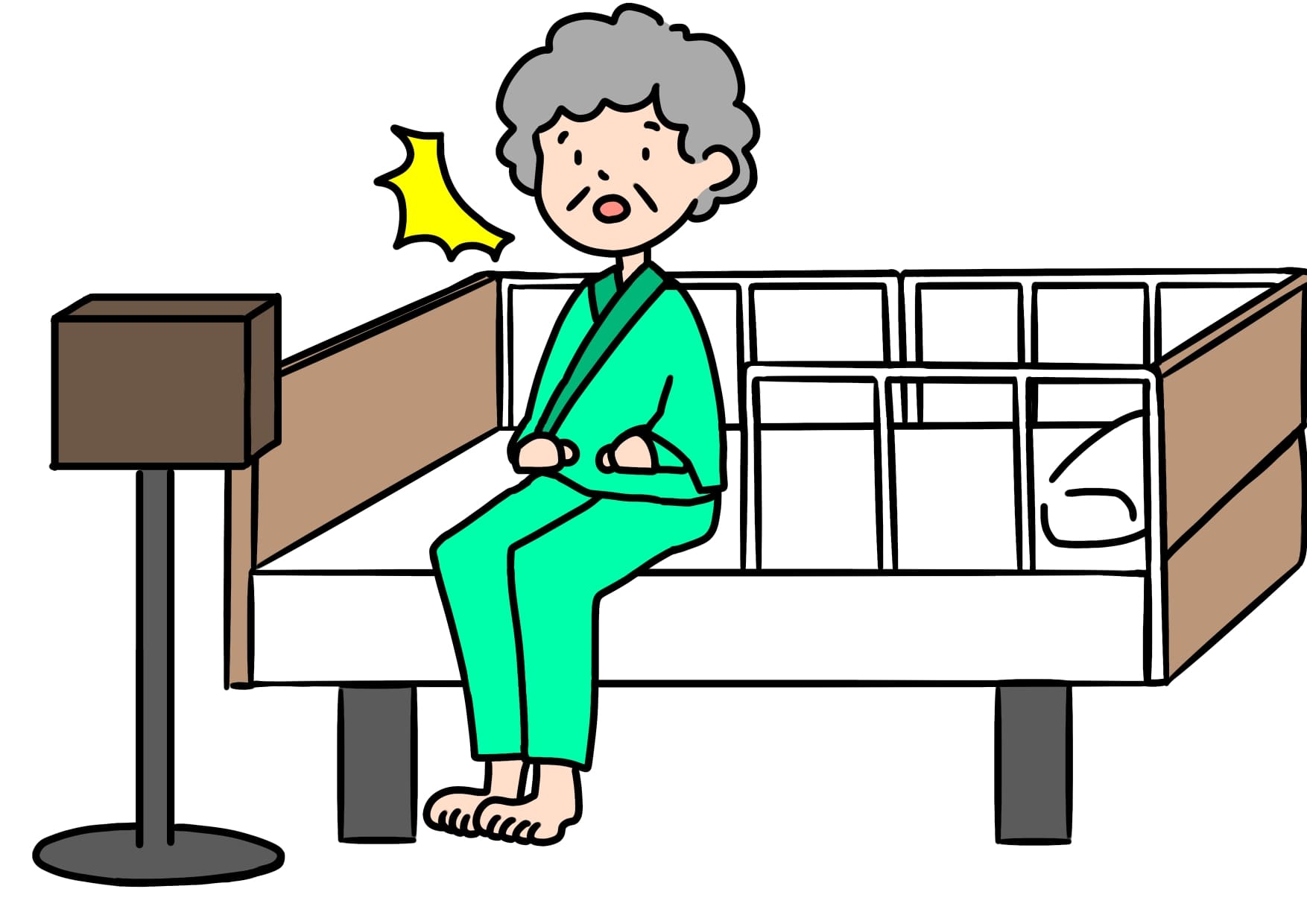
離床センサーのデメリットは次の通りです。
● 誤報により不要に訪室してしまう
● 段差やコードによりつまずく
● センサーを避けられて反応しない
● 断線する可能性がある
デメリットを補う対策も合わせて解説します。
誤報により不要に訪室してしまう
離床センサーは患者さん・ご利用者の動きを検知するものですが、誤報により不要に職員が訪室してしまうことがあります。その結果、職員の負担が増加するデメリットが存在します。
患者さん・ご利用者が頻回に離床センサーを踏んだり、面会中や介助中にスイッチを切り忘れたりしているためです。
対策
介助時や面会時にスイッチをオフにすれば不要な検知はありません。ただし、スイッチの入れ忘れには十分注意が必要です。「一時停止ボタン」が搭載されている離床センサーであれば、この機能の活用をおすすめします。
患者さん・ご利用者が頻回に離床センサーを踏んでしまうのであれば、マットの位置を適切であるかを検討しましょう。予算がある場合、見守りカメラなど誤報の少ない離床センサーに変更する方法もあります。
段差やコードによりつまずく
離床センサーには段差やコードにつまずく転倒リスクがあります。離床センサーには数ミリの厚みがあるのと、電源やナースコールにつなげるためのコードが存在するためです。
対策
離床センサーは滑り止めシートなどで覆い、四方はテープで固定することにより段差を少なくできます。コードはできるだけベッドや床頭台の下などに固定すると、つまずくリスクを減らせます。無線タイプの離床センサーを導入しても良いでしょう。
センサーを避けられて反応しない
患者さん・ご利用者が離床センサーを避けて反応しない場合があります。患者さん・ご利用者のなかには、離床センサーを踏むと職員が来ることを察知される方もいるためです。
対策
ベッドを壁に寄せたりベッド柵を用いたりすることで、離床センサーが敷かれた場所を踏まないと、ベッド上から降りられないようにする誘導方法があります。離床センサーの上に履き物を置くように取り決めても良いでしょう。
断線する可能性がある
有線の離床センサーの故障で多いのが断線です。患者さん・ご利用者だけでなく職員なども、コードを踏んだり引っ張ったりしてしまうためです。
対策
踏まれないようにベッドや床頭台の下にコードを通しましょう。ベッド移動の際にコードが引っ張られていないかも注意してください。断線が頻回に生じるのであれば、無線タイプの離床センサーの導入がおすすめです。
2.離床センサーのメリット
● 転倒・転落を予防できる
● 夜間徘徊を防ぐ
● 行動パターンを把握できる
それぞれ解説します。
転倒・転落を予防できる
離床センサーは、歩行や立位が不安定な方の転倒・転落を予防できます。ご利用者が立ち上がったり歩き出したりする前に検知できるためです。実際に離床センサーの使用を始めると、転倒・転落率が7.9%減少したというデータもあります。
ベッドサイドや自室の入り口付近に設置するのが基本的な利用方法です。立ち上がりまでに行動が早い場合は、離床センサーでは間に合わない可能性があります。その場合は、ベッド柵に取り付けるタッチコールや、ベッド降り口に敷くベッドサイドセンサーを利用したほうが良いでしょう。
出典:J-STAGE「離床センサー使用による転倒・転落予防の有効性」
夜間徘徊を防ぐ
離床センサーはご利用者の動きを検知できるため夜間徘徊を防げます。徘徊行動を予測しておけば、他のご利用者とのトラブルや離院を未然に防ぐことが可能です。
自室で行動が活発な方の場合、ベッドサイドに設置すると頻回に検知してしまいます。自室の入り口付近に設置すると良いでしょう。
行動パターンを把握できる
離床センサーはご利用者の行動パターンを把握できます。
例えば次の通りです。
● 徘徊行動はあるが入り口に設置した離床センサーはほとんど作動しないため、自室意外での徘徊行動は少ない
● センサーの作動があってもポータブルトイレを利用しているだけであり危険行動は見られない
病院や施設内、または転院先のサービス担当者と共有すれば、ご利用者にとって最適な援助につなげることができます。
離床センサーを活用する際は、行動把握や転倒・転落予防など目的を明確にすることが大切です。設置場所も転倒予防であればベッドサイド、行動把握であれば自室の出口付近など異なります。そもそも離床センサーが適しているのかも検討して、患者さん・ご利用者にとって最適な援助につなげましょう。
3.【種類別】離床センサーのメリット・デメリット
次に、離床センサーの種類別のメリット・デメリットを解説します。
| 種類 | メリット | デメリット |
| クリップセンサー | 起き上がり動作を検知できるため、迅速に対応可能である | クリップを取ってしまう方には適さない |
| タッチセンサー | ベッド柵に取り付けるため、起き上がり動作を検知できる
ベッド柵を外す方にも有効である |
不要にベッド柵を触れてしまう方は誤報が多くなる |
| ベッドサイドセンサー | ベッド端の降り口にパッドを敷くセンサーで限定的な動作を検知できる
起き上がりや寝返りなどによる誤報が少ない |
置き方や向きを間違えると作動しない可能性がある |
| カメラセンサー | 画像解析で検知できるため誤報が少ない
スタッフステーションからご利用者の様子を把握できる |
ご利用者が監視されていると感じる可能性がある |
| 超音波・赤外線センサー | 超音波や赤外線で検知する
設置場所で検知する動作を調整できる |
離床センサーよりも価格が高い |
離床センサーの種類の詳細を知りたい方はこちらを参考にしてください。
▼離床センサーとは?種類や看護・介護の際の注意点を解説!
4.離床センサー利用時の注意点やポイント

離床センサー利用時の注意点やポイントは次の通りです。
● スイッチの切り忘れに注意する
● 離床センサーを過信しない
それぞれ解説していきます。
行動パターンを把握できるスイッチ入れ忘れに注意する
介助後や面会後にスイッチを入れ忘れてしまうケースが多いです。離床センサーがオフのままで作動しなければ、転倒・転落などにつながる恐れがあります。
スイッチ入れ忘れを予防するための対策の一例は次の通りです。
● 設置している部屋から離れる際は、必ずスイッチの確認する
● 「スイッチ確認」の貼り紙を目に入る位置に貼る
行動パターンを把握できる離床センサーを過信しない
「離床センサーを設置しているから安全」という過信には注意が必要です。「離床センサーが故障している」「患者さん・ご利用者がスイッチをオフにしてしまった」などの思わぬトラブルが発生している可能性があるためです。
離床センサーを過信せず、勤務時間帯ごとに訪室して患者さん・ご利用者の状態やセンサーの設置状況を確認する必要があります。また、定期的に患者さん・ご利用者の状態を確認して離床センサーの設定や種類、使用の有無を見直しましょう。



