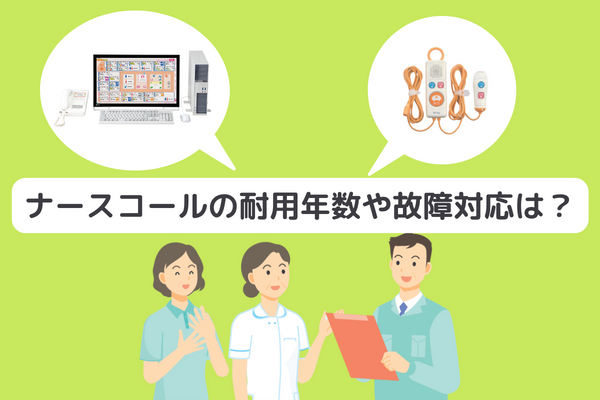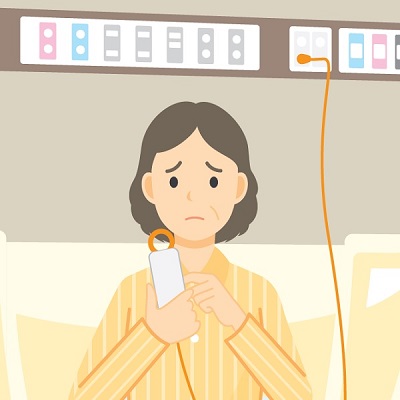Contentsお役立ち情報・製品動画
お役立ち 2023.02.03
家庭用ナースコールの種類や注意点、業務用との違いって?
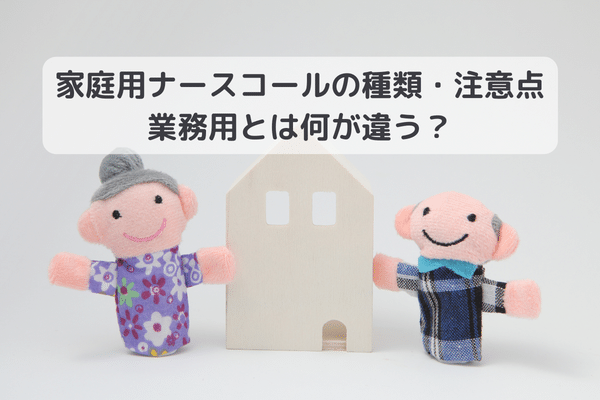
病院や介護施設などに導入されているナースコールですが、家庭用のナースコールもあることはご存知でしょうか。
家庭用ナースコールとは、要介護者(介護が必要な方)が在宅で生活をする際に、介護者を呼ぶことや連絡するために用いるナースコールです。家庭用ナースコールは、様々な種類や機能があり、ご家庭の状況に合わせて選択することが可能です。
一方で、病院や介護施設などに導入されている業務用ナースコールは、看護師さんや介護士さんを呼ぶ機能だけでなく、様々な機能があります。
そこで今回は、家庭用ナースコールの概要から種類・注意点、そして業務用ナースコールとの相違点について詳しく説明していきます。
▼目次
1.家庭用ナースコールとは?
2.家庭用ナースコールはどんな種類や機能があるの?

種類1:押ボタン式
押ボタン式は、送信機のボタンを押すと受信機のブザーが鳴るナースコールです。要介護者が介護者を呼ぶときに用いられます。ボタンのデザインがシンプルなものが多く、高齢者の方が簡単に押しやすくなっています。また、首からぶら下げるなどのタイプがあるのが特徴です。
種類2:通話可能なタイプ
通話可能なタイプは、ボタンを押すと呼出機能だけでなく、音声通話もできるナースコールです。ナースコールを用いて、意思の疎通を図ることができます。
ただし、注意点として、通信環境がない場合は設置できないことがあります。
種類3:複数の場所に設置できるタイプ
送信機に対し、複数の受信機を設置できるナースコールもあります。トイレや浴室、寝室、リビングなど部屋ごとに設置する場合や介護者が複数いる場合に用いることがあります。
無線の範囲や受信機の台数はメーカーによって異なるので、事前に確認しましょう。
種類4:無線通話可能なタイプ
無線機能で呼出が可能なナースコールです。要介護者と介護者が、それぞれ通話機を用いて連絡を取ります。無線のため、持ち歩くことも可能です。
ただし注意点として、電波が届かない場所にいると呼出や通話が出来なくなることがあります。
種類5:スマホ連動型
スマホ連動型は、ナースコールを押すと介護者のスマートフォンに連動して、呼出や通話ができるナースコールです。1人暮らしの方や日中のみ1人で過ごす方が家族への連絡手段として用いることが出来ます。
Wi-Fi接続で使用可能となるため、自宅内の通信環境が必要となります。
家庭用ナースコールの機能
一部の家庭用ナースコールの商品では、防水機能付きや屋内外の設置が可能なもの、首からぶらさげるタイプ、カメラの映像を用いて通話が出来るものもあります。また電源は、コンセントに差し込むタイプや電池式、自家発電式などがあります。
家庭用ナースコールは様々な種類や機能があるので、ご家庭に合ったものを使用しましょう。
3.家庭用ナースコールの注意点
家庭用ナースコール購入時・設置時・使用時に気を付けることを解説します。
購入時の注意点
家庭用ナースコール購入時の注意点は、名称と必要な機能です。名称や商品名は、家庭用ナースコールとは限りません。「緊急コール」「緊急通報システム」「介護コール」「ワイヤレスコール」などのように、「ナースコール」と名称されずに販売されていることがあります。
そのため、名称で決めるのではなく、必要な機能があるものを購入するようにしましょう。
設置時の注意点
家庭用ナースコールを設置する際、取り付ける場所に気を付ける必要があります。押せない場所にあっては意味を成しません。そのため、ナースコールを設置する場所は、確実に要介護者の手が届き、安全なところに設置をしましょう。
無線の場合は、設置する位置によってつながりやすさが変化するため、ナースコールの動作を確認しながら設置することを推奨します。
使用時の注意点
ナースコールの故障や電池切れなどの確認をするために、定期的に鳴らして動作の確認をすることが大切です。
また、要介護者に家庭用ナースコールの送信機を携帯してもらう習慣付けをします。家庭用ナースコールの使用に慣れてくると、要介護者だけでなく、介護者が受信機もしくはスマートフォンを携帯しなくなることがあるので気を付けましょう。
無線の場合は、有線と比較すると電波の影響で動作が不安定になることもあります。ナースコールの音と他の音の判断がつかずそのままにしていたら、介護者からのナースコールを放置し、重大な事故に繋がってしまったということもあるため、過信しすぎないようにしましょう。
これらの注意点を踏まえ、家庭用ナースコールを安全に設置・使用するようにしましょう。
4.家庭用ナースコールと業務用ナースコールの違いとは?

様々なシステムと連携できる
例えば、トイレで排泄後、患者さん・ご利用者が便座から離れようとするとセンサーが察知しナースコールに連動する、ということができたりします。
また、生体情報モニタとスマートベッドシステムが連動することで、ベッドで寝ている患者さん・ご利用者の呼吸数や心拍数、睡眠、覚醒、離在床を把握することが可能です。ナースコールと連動しているため、異常時はナースコールが鳴り、患者さん・ご利用者の異常や急変を素早くキャッチします。
さらに、地震や火災などの災害時に介助が必要な患者さん・ご利用者がいることを知らせる目印灯として病室の廊下を点灯することもできます。
業務の状況把握
スタッフステーションには、ナースコールディスプレイが設置してあり、患者さん・ご利用者のケアに必要な情報などが一覧表示されています。患者さん・ご利用者の状態から、呼出の理由が分かるため対応しやすくなります。
複数の呼出時の対応
ナースコールは、スマートフォンや電子カルテ用ノートパソコンなどの端末と連動できます。
そのため、複数のナースコール呼出があっても画面に複数表示されます。すぐにボタンを押した患者さん・ご利用者の情報が確認できるので、優先順位を把握しながら対応が可能となります。
また、各端末と連動していることで、スタッフステーションに戻らなくても呼出理由の記録や履歴、患者情報の参照に役立ちます。
ナースコール履歴管理
ナースコール履歴管理とは、病棟または病院全体で時間帯別の呼出回数や患者さん・ご利用者別の呼出回数がグラフ化できるシステムです。呼出回数の多い時間の把握から業務の改善や呼出の多い患者さん・ご利用者の看護計画の見直しに用いられています。